糖尿病の人はがんになりやすい?大腸がんの発症リスクの関係と予防
- heiwamed0002team
- 2021年10月5日
- 読了時間: 4分
更新日:3月23日
40歳以上の人の4人に1人、全国では1000万人もいるとされている糖尿病。 治療中の人は約76%と言われ、まだまだ糖尿病が重大な病気と考えられていない日本ですが、合併症の怖さをご存知でしょうか。 糖尿病は「網膜症」「腎症」「心筋梗塞」「脳梗塞」などの血管系の合併症をひきおこします。糖尿病を治療してこれらの合併症を予防することが大切です。

これは血糖値が高い状態が長く続く糖尿病により、血管がボロボロになっていまうことから起こります。
では、糖尿病の人はがんになりやすいのでしょうか。 答えはYESです。糖尿病の人は、そうでない人に比べてがんの発症リスクが高い傾向にあります。糖尿病の人は、そうでない人に比べてがんの発症リスクが高い傾向にあります。
糖尿病患者の場合膵臓、肝臓、大腸のがんリスクが上昇
日本糖尿病学会と日本癌(がん)学会の合同委員会による報告では、2型糖尿病患者はそうでない人に比べると全体で1.2倍がんの発症リスクが高い傾向になることがわかりました。
では、なぜ糖尿病の場合、癌リスクが高くなるのでしょうか。
詳しい原因はまだ解明されていませんが、以下のような可能性が提唱されています。
血糖値が高い
高血糖により、酸化反応により引き起こされる、カラダにとって有害な作用=酸化ストレスが促進され、DNAにダメージを負い癌細胞が増殖する可能性があるとされています。血糖値が高いことによる直接の作用です。
血液中のインスリン濃度が高い
インスリンが効きにくい糖尿病患者は血液中のインスリン濃度が高くなっています。
インスリンは血糖値を下げるホルモンとして有名ですが、血糖値を下げる以外に過剰なインスリンは癌細胞の増殖を促進する作用やがんの転移を促進する働きもあります。インスリンは増殖因子としての働きもゆうするのです。
炎症
2型糖尿病の方では、肥満の方も多く、慢性的な炎症があると考えられます。慢性の炎症は、発がんのリスクと考えられています。
糖尿病とがんに共通するリスクは生活習慣によるもの
その他、2型糖尿病においては生活習慣病であり、がんとの因果関係の原因がはっきりしなくとも、共通する項目があります。
2型糖尿病の原因
2型糖尿病の場合多くは以下のような原因が考えられます。
肥満

肥満は糖尿病にとって一番の危険因子であり、あらゆる病気を引き起こしやすく、発がんリスクも確実に上げる要因となっています。
不摂生な食事

バランスのよい食生活を取ることは糖尿病にならないために重要なことです。 肉類の接種が少なく、野菜や果物、食物繊維が多い食事を心掛けることはインスリン感受性を改善、2型糖尿病の予防にもなります。
運動不足
運動不足になることは先の肥満にも繋がりやすく、これにより、便秘なども引き起こしやすいです。運動をして身体活動を向上させることは、は結腸癌、閉経後の乳がん、子宮内膜がんのリスクを下げることもわかっています。
喫煙

喫煙は肺がんだけでなく、口腔・咽頭、喉頭、鼻腔・副鼻腔、食道、胃、肝臓、膵臓、膀胱および子宮頸部などのがんになりやすいこともわかっています。 もちろん、2型糖尿病の発症リスクも上げます。
糖尿病の診察だけでは発がんはわからない
糖尿病患者さんががんにならないためには血糖値コントロールをしっかりすることが大事です。
糖尿病患者さんの中には定期的に病院に行っているから、定期健診は必要ないと思っている方もいらっしゃいます。
しかし、がん検査と糖尿病の検査は全く違います。
早期発見のためにもがん検診はしっかり受けましょう。
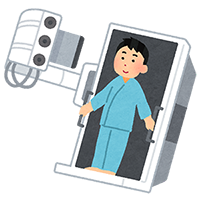
胃がん、子宮がん、肺がん、乳がん、大腸がんの5種類のがんについては、がん検診を厚生労働省が推奨しており、西宮市でも集団検診を行っています。 西宮市集団検診
40歳以上の人は胃がんだとバリウム、大腸がんだと便潜血検査で検査が可能です。 1年に1回を目安に定期的に健康診断を受ける習慣をつけることが大事です。
糖尿病専門病院ではがんの早期発見のために、定期的に腹部エコー検査、便潜血検査、胃カメラなどの検査をすることがあります。
血糖コントロールはもちろん、急激な体重減少などはがんの危険性をはらんでいます。特に貧血を認める場合、胃がんや大腸がん含め消化管からの出血がないか胃カメラや大腸カメラでのチェックが大切です。
糖尿病で病院に通っているからと、安易に考えず、定期的な検査を心掛けましょう。
